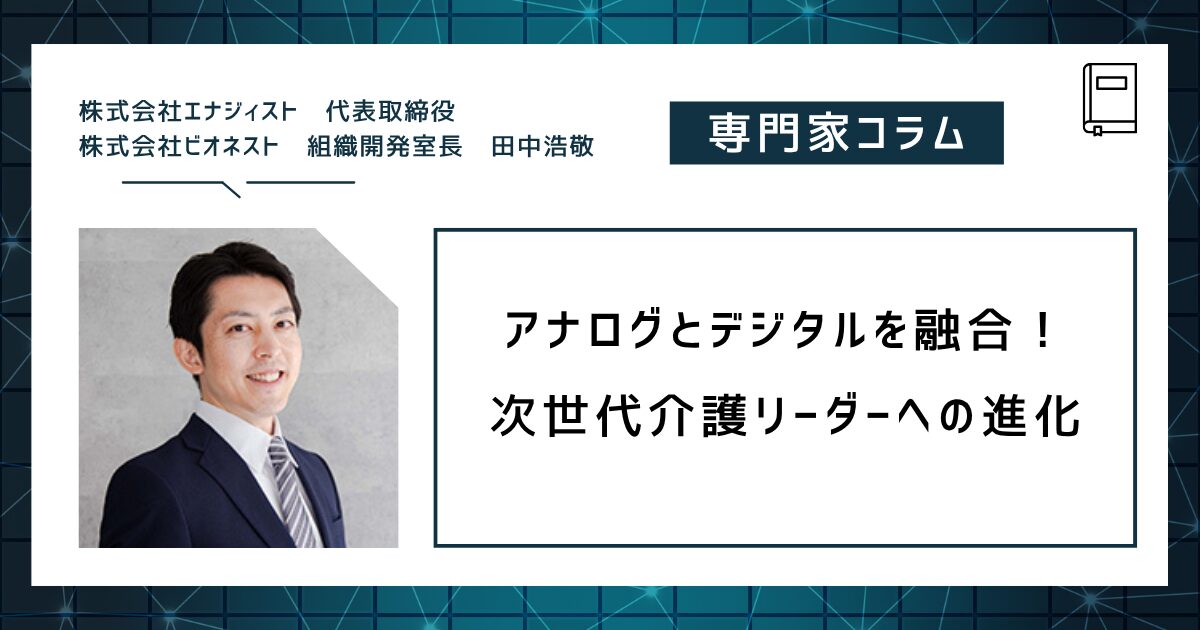介護現場におけるDXは、単なるツール導入ではなく、“人”を中心とした変革です。その中でも重要な役割を担うのが、現場と経営の橋渡しをするミドルリーダーです。
現場を理解しながら、デジタルの活用を推進できるリーダーの育成こそが、DX成功のカギとなります。
本コラムでは、アナログとデジタルの力を融合し、次世代の介護リーダーへと進化するために必要なビジネスリテラシーの視点について専門家の立場から解説します。
専門家の視点から
私は現在、全国500事業所、従業員5000名規模で介護施設等を運営する大手福祉事業会社にて「組織開発室長」を務めつつ、兼務している「子会社 代表取締役」として外部企業へ人材・組織開発コンサルティングや研修をサービス提供しております。
専門分野は、「ミドルマネジャー起点の組織変革」です。成長期又は成熟期にある企業のミドルマネジャーを「経営と現場の組織結節点」として進化させるために「現役実践知を活かしたスキルと基準と覚悟の3点強化」を得意としております。
田中 浩敬(株式会社エナジィスト 代表取締役 / 株式会社ビオネスト 組織開発室長)
介護DXについて
「現場職員のビジネスリテラシーを底上げすること」が、介護DXの成否を分ける!と確信しております。
私は、「介護業界外から来た人間」です。前職では、「日本を代表するトップ企業」の人材・組織開発コンサルティングに従事していました。
だからこそ、参画当初は大きな違和感を持っていました。その違和感の正体こそ、「介護現場にビジネスパーソンが圧倒的に少ない」ということです。通じない「ビジネス用語」、「営業活動」という言葉への抵抗や拒否感、「接遇やサービス」という言葉への関心の低さなど。
命や健康の維持向上という社会的価値を創出する「ヘルスケアパーソン」は沢山おられますが、差別化、サービス品質などの経済的価値を創出する「ビジネスパーソン」は少ないと感じました。
介護DXに興味がある現場職員の皆さんへ
介護DX進めたいけど、思うようにいかない…こんな悩みありせんか?
DXの前に、BXです!BXとは「ビジネス・トランスフォーメーション」のこと。
介護を「ヘルスケア」から「ヘルスケアビジネス」に進化させ、DXを加速しましょう!ビジネスリテラシーを底上げすれば、「自ずと」DXの機運が高まります。
なぜDXの前に、“BX”が大事だと考えるのか?
介護を含む福祉業界には、社会的価値と経済的価値の両立、いわゆる「CSV(Creating Shared Value:共通価値の創造)」の考え方が浸透していないことが原因であると考えます。
その根本的原因は、ビジネス基礎力、すなわち、「ビジネスリテラシーの不足」です。ビジネスリテラシーが不足していると「CSV」「DX」「生産性向上」などの「ビジネス用語」が機能せず、「経営→管理→現場の一気通貫のマネジメント」が機能しません。 経営が使う「ビジネス用語」を理解し、現場で使う「介護業界用語」への翻訳を行う。そのために、介護を「ヘルスケア」のみでとらえるのではなく「ヘルスケアビジネス」として捉える組織風土を「前提として」醸成する必要があるのです。

BXが進めば、経営と現場の「課題解決の方向性」が一致する。
現場は「人材をもっと採用して欲しい」と意見を上げますが、経営は「人材をもっと活用して欲しい」考えております。
また、現場は「もっと給料を上げてほしい」と意見を上げますが、経営は「もっと給料を最適化したい」と考えております。 経営も現場も「人材不足」と「処遇改善」の2つを重要課題として認識していることは同じですが、経営と現場によって「解決の方向性」が異なる。この方向性を「揃える」ことために、現場職員のビジネスリテラシー向上が必要なのです。
介護DXが“失敗”に終わるのはなぜか?
介護DXを経営からの「トップダウン」で進めては失敗します(現場でのDXには、「現場職員の主体性」が必要であるため)。
また、ビジネス視点が弱い状態での現場からの「ボトムアップ」でもうまくいきません(DXから「真の価値」を生み出すためには「ビジネス視点」が必要なため)。
要となるのは、「経営と現場の組織結節点となるミドルマネジメント層(エリアマネジャーや管理者)」です。現場を熟知し、経営を理解しているミドルマネジメント層による「ミドルアップダウン」での推進が大事です。
そのためには、大前提としてミドルマネジメント層の「ビジネスリテラシー向上」が必要です。理念体系、マネジメント、リーダーシップ、ビジネスモデルなどのビジネス用語を正しく理解し、経営の言葉を理解し、現場に「翻訳」して落とし込む。
その結果「介護DXという経営方針の本質的な理解」が促され、経営方針を現場に「適切に」落とし込む「現場フィット」が可能になります。
「生産性向上」を振りかざして、現場から“クレーム”をもらった苦い経験
数年前、「介護現場の生産性向上」という錦の御旗の元、私も介護現場にイノベーションを起こすためのパワーワードとして「生産性向上」というワードを多用していた時があります。
その時に、ある認知症グループホーム管理者Fさんからもらったクレーム(≒フィードバック)が私のスタンスを変えました。
「田中さんは、事あるごとに『生産性向上』とおっしゃいますが、そんなことは現場職員も百も承知なんです。この業界は、ずっと人不足なのですから。今いる人数でどう回せばよいのか、常に意識しています。だから、生産性向上は響かないのです。では、どの言葉が響くのか?それは『自立支援』です。この想いが、介護現場を支えている職員の『誇り』であり『モチベーション』です。」
このクレームをもらった時、私はハッとしました。「生産性向上」というビジネス用語を「そのまま」伝えても、現場職員の「心」を動かすことは出来ないのだと。
現場職員が何を大事に、何を軸に、何にやりがいを感じて働いているのか?その「本質」をとらえ、その本質にこちらがマッチさせる。すなわち、「ミドルマネジメント層の翻訳機能」こそ 大事なのだと。そのためには、経営が使う「ビジネス用語」を、現場が使う「介護業界用語」を翻訳し、橋渡しする必要があるのです。分かりやすい具体例を挙げると「売上を上げる」という言葉ではなく、「当施設を利用して笑顔で楽しく自立して過ごせる高齢者を地域に増やす」といった具合に です。
「ビジネスリテラシーを向上する教育機会」を増やす!
まずは「法定研修」以外のビジネスリテラシー教育として「法定外研修」を実施することをお勧めします。法定研修だけでは、ビジネスリテラシーは向上されません。問題解決思考、プレゼンテーション、ロジカルコミュニケーションなどのビジネス教育を通じて、介護現場にヘルスケアビジネスパーソンを増やしましょう。
2030年頃の未来から逆算して今を考える「未来予測研修」やDXトライアングルなどを理解する「DX基礎研修」も効果的です。
また、余力があれば、ぜひ「異業種連携」にも挑戦ください。介護業界以外の一般ビジネスをしているビジネスパーソンと企画を共創し、現場職員と触れ合う機会を増やします。業界外の知見やスキルに触れることで、「自ずと」ビジネスリテラシーが向上していきます。
“ミライの介護”は、みんなで共創する!

介護DXを含む介護現場の課題は、介護業界・介護従事者だけの「業界課題」ではありません。世界一の高齢化先進国となった日本の「すべての業界・すべての国民」に関わる「国家課題」です。
であれば、業界外との連携、業界外企業が作り出した「テクノロジーの活用」は必須です。
介護現場にいる自分たちが「国家課題のフロントラインにいる」というマインドで、ビジネスリテラシーを底上げし、共にDXを進めていきましょう。
著者プロフィール・関連リンクのご案内
田中 浩敬(株式会社エナジィスト 代表取締役 / 株式会社ビオネスト 組織開発室長)

全国500事業所、従業員5000名規模の大手福祉事業会社にて「現役」で「組織開発室長」を務めつつ、兼務している「子会社 代表取締役」として外部企業の人材・組織開発コンサルティングや研修実施にも携わるパレレルワーカー。
「現役実践知」を活かした伴走支援スタンスが、理論偏重・事例偏重のコンサルタントや研修講師と「一味違う」と好評を得ている。 零細企業から日本を代表するトップ企業まで「7年間」全規模の人材・組織開発コンサルティングで得た「知見」を、日本の社会課題解決に活かしたいと思い、介護福祉業界に飛び込む。「ミドルマネジメント層の採用・育成」を主軸に、「異業種連携」や「産学連携」を多数手がけ、共創で介護イノベーションを起こす活動を多数展開している。
《運営メディア》
《メディア掲載実績》
- 【経済産業省】公式ホームページの「ヘルスケアサービス社会実装事業報告書」にて活動紹介
- 【大阪市】公式ホームページにて「介護イノベーション共創ワークショップ」講師・ファシリテーターとして紹介
- 【KDDI】運営research atelier「FUTURE GATEWAY」にて「先進生活者=越境走者(ランナー)」として活動紹介
《その他》
- 【大阪産業局・大阪産創館】運営「新規事業開発窓口」登録メンター
- 【ATCエイジレスセンター】主催「“ミライの介護”共創ワークショップ」講師兼ファシリテーター
- 【オランダ総領事館・大阪市経済戦略局】主催「オランダ×日本 介護イノベーション共創ワークショップ」講師・ファシリテーター