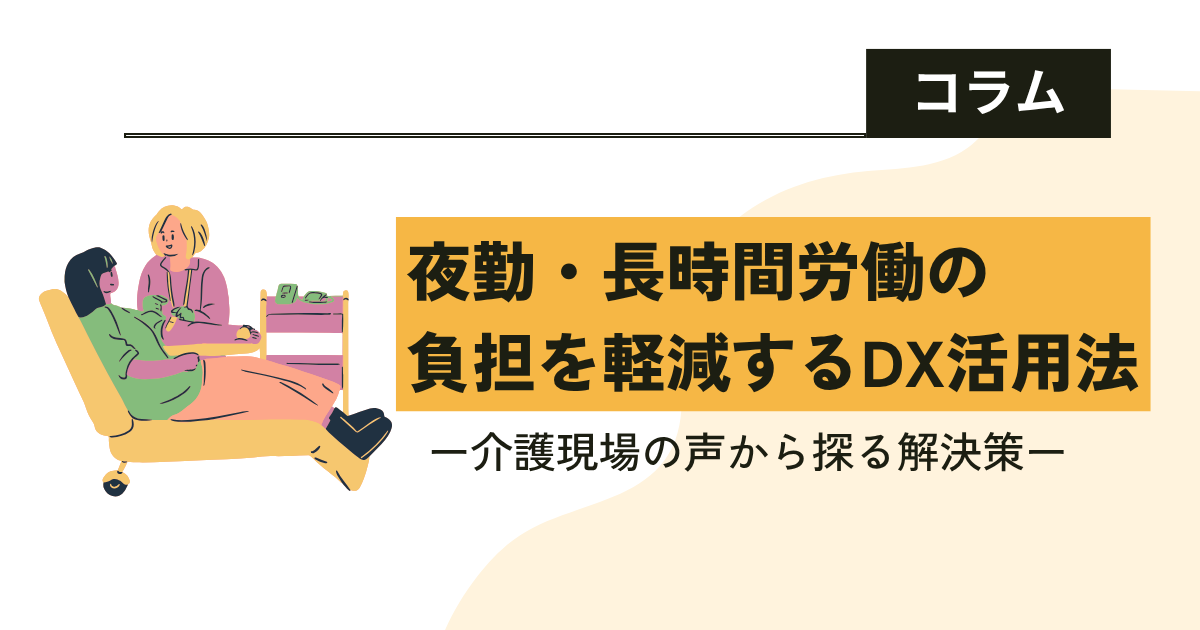介護現場が抱える深刻な負担
介護業界では慢性的な人材不足が続いており、その影響は夜勤や長時間労働という形で現場の職員に大きな負担を与えています。夜間は入居者の急変対応や巡回業務が不可欠であり、限られた人数で複数の利用者を支えなければなりません。
結果として、心身の疲労が蓄積し、離職率の高さや人材定着の難しさにも直結しています。
こうした現状を打破するために注目されているのが、DX(デジタルトランスフォーメーション)の活用です。
DXは単なる効率化にとどまらず、介護の質を高めながら職員の負担を軽減する可能性を秘めています。
第1章:現場の声に見る「負担の正体」
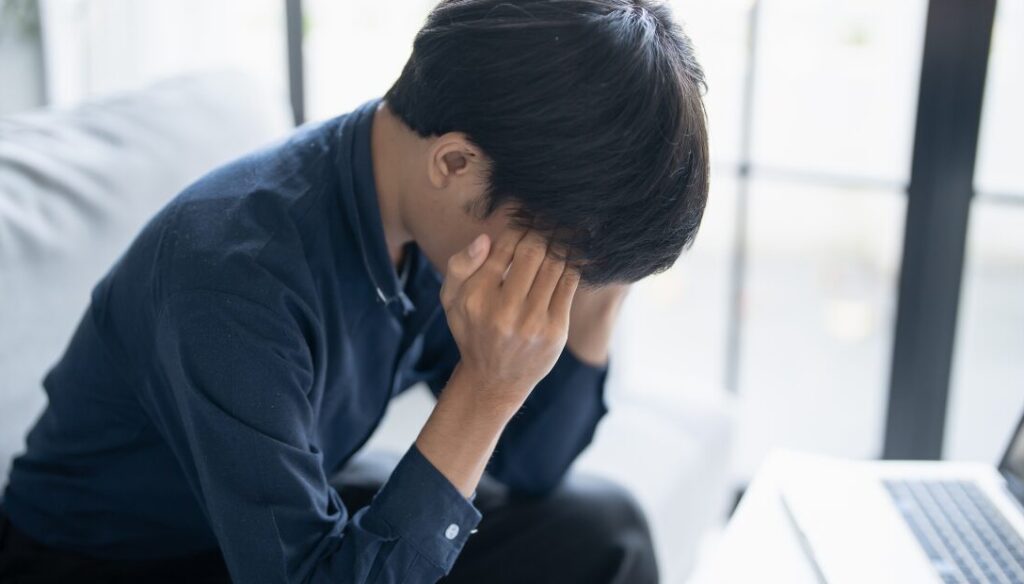
介護職員が口を揃えて挙げるのが、「夜勤業務の過酷さ」 です。
日勤と比べて人員配置が少なく、1人当たりの負担が格段に増す夜勤では、身体的な疲労だけでなく精神的な緊張感も強くのしかかります。
利用者が眠っている時間帯だからこそ、静けさの裏に潜むリスクがあり、突発的な事態に備え続ける必要があります。
ここでは、職員の声から浮かび上がる主要なストレス要因を整理します。
記録業務の多さ
夜勤帯でも欠かせないのが記録の作成です。利用者一人ひとりの睡眠や排泄、服薬状況、体調の変化などを細かく残すことがルールとして義務づけられており、これが介護保険制度上の請求や事故防止の観点で重要であることは言うまでもありません。
しかし現場からは「重複が多い」「実態に合っていない」という声が絶えません。
たとえば、日中と夜間で似たような内容を別様式に記録する、紙に書いた後にシステムへ二重入力する、といった作業が頻発します。限られた人員で対応する夜勤中にこうした手間が積み重なることで、ケアに向けるべき時間が削られてしまうのです。
疲労が溜まる明け方にまとめて記録しようとすると記憶が曖昧になり、ヒューマンエラーや記録漏れのリスクも高まります。
「必要だと分かっていても無駄が多い」というジレンマが、夜勤をより過酷なものにしています。
巡回の負担
もう一つ大きな負担は定期巡回です。
夜間は入居者の転倒や体調変化のリスクが高く、一定時間ごとに居室を回ることが不可欠です。
しかし、数十人規模の利用者を1人や2人で見守る施設も少なくなく、巡回には膨大な時間と体力が必要になります。
仮眠を取る余裕はほとんどなく、連続勤務を繰り返すことで睡眠不足が慢性化します。
巡回の多くは「異常なし」を確認する作業で終わるものの、そのために職員は深夜の静まり返った廊下を歩き続けるのです。
突発的な対応
さらに職員を消耗させるのが突発対応です。
ナースコールが鳴った瞬間、軽微な要件か急変かは現場に行かなければ分かりません。
しかも、複数のコールが同時に鳴ることもあり、そのたびに優先順位を瞬時に判断する緊張を強いられます。
静かな時間帯が一変し、一晩のリズムを乱すこともしばしばです。
こうした予測不可能な出来事への対応は、常に「次は何が起こるか」という不安感を伴い、精神的な疲弊を引き起こします。
人員不足による心理的圧迫
夜勤は日勤に比べて人員が少なく、1人でフロア全体を任される ケースもあります。
そのため、同時に複数の対応が必要になった場合、どうしても遅れが生じ、利用者に不安を与える可能性があります。その責任感の重さが職員を追い込み、「自分一人で守らなければ」という孤独なプレッシャーを感じる場面も少なくありません。
このように夜勤の業務は、記録・巡回・突発対応・人員不足という複数の要因が絡み合い、体力的・精神的に極めて過酷です。利用者の安全を守る使命感があるからこそ続けられているものの、職員の心身への負担は計り知れません。
この「負担の正体」を解き明かすことが、DX活用を考えるうえでの出発点となります。 筆者自身も現場に立った際、書類作成に追われて利用者と向き合う時間が削られることに大きなジレンマを感じました。
ときには疲労から、普段なら大切にできる利用者との会話が煩わしく、鬱陶しく思えてしまう瞬間もありました。
必要性を理解しつつも「無駄だ」と感じる作業に時間を取られる中で、虚無感に襲われた経験もあります。
こうした感覚は、多くの介護職員が抱える切実な思いに重なるのではないでしょうか。
第2章:DX活用による解決の方向性

DXは「人が担っていた業務をすべて機械に置き換える」ことだけを意味するものではありません。
介護という分野は、人と人との関わり、つまり“ケア”そのものが本質にあります。
だからこそ単純な置き換えではなく、人とテクノロジーの協働 によって職員が利用者とより深く向き合える環境をつくることが重要です。
DXの導入は「職員の仕事を奪う」ものではなく、「人にしかできない仕事に集中できるよう支援する」取り組みといえます。
介護分野におけるDXの方向性は、大きく以下の3点に整理できます。
1. 業務の効率化
記録業務や巡回といった定型的な作業は、ICTを活用することで大きく効率化できます。
たとえばタブレットを用いた電子記録システムは、夜勤中にリアルタイムで簡単に入力でき、紙への手書きや二重転記の手間を削減します。
また、見守りセンサーやカメラを導入すれば、必要なときだけ駆けつける対応が可能となり、無駄な巡回の負担を減らせます。これにより、職員は「単純作業に追われる時間」から解放され、利用者のケアに集中できます。
2. 安全性の向上
DXの導入は職員の負担を軽くするだけでなく、利用者の安全にも直結します。
センサーやAIを活用することで、心拍数や呼吸数、離床の兆候などをリアルタイムに把握でき、夜間の事故や体調急変の見落としを防ぐことができます。
従来は「人の目と耳」に頼っていた部分がテクノロジーに補完されることで、より精度の高い観察と迅速な対応が可能になります。
これは単に職員を楽にするためではなく、利用者の安心感を高め、介護の質を守るうえでも大きな意義を持ちます。
3. 働きやすい環境の実現
DXは業務の一部を自動化するだけでなく、チーム全体の働き方そのものを改善する力 を持っています。
シフト管理システムを活用すれば、職員の希望やスキルを反映しながら公平な勤務調整ができ、管理者の負担を軽減できます。
また、情報共有をクラウドで一元化することで、夜勤と日勤の間で申し送りの齟齬を防ぎ、チームワークを高めることにもつながります。
結果的に「属人的な働き方」から「チームで支える介護」へとシフトし、職員が安心して働ける職場環境が整います。
このように、DXは単なる効率化のための技術ではなく、人とテクノロジーが補い合う関係を築くこと にこそ意義があります。
定型的な業務をICTが支え、安全性をAIが担保し、働きやすさをシステムが整えることで、職員は利用者とのコミュニケーションやケアといった“人にしかできない業務”に集中できます。
その結果、介護の質が高まり、利用者の満足度と職員の働きがいが両立する未来像が見えてくるのです。
第3章:具体的なソリューションと事例
見守りセンサーの導入
夜間の巡回を大幅に減らすのが「見守りセンサー」です。
ベッドに設置するだけで心拍数や呼吸数、離床状況を常時モニタリングでき、異常があれば自動的にアラートが届きます。
従来は職員が数時間ごとに各居室を回り、異常がないかを一人ひとり目で確認していました。しかしこの方法は利用者を起こしてしまうリスクもあり、また職員にとっては「異常がないことを確認するための巡回」に多くの体力と時間を費やすものでした。
センサーの導入によって、必要なときだけ駆けつければよくなり、巡回回数を大幅に減らすことができます。
ある施設では、1夜勤あたりの巡回回数が従来の半分以下になり、職員の休憩時間確保や睡眠不足の改善につながったと報告されています。
厚生労働省の実証事業でも、見守りセンサー導入により夜勤業務時間が約25%削減されたとのデータが示されています。(出典:厚生労働省「介護現場におけるICT導入実証事業報告書」 mhlw.go.jp)
電子記録システム・音声入力
次に効果を発揮するのが、電子記録システムと音声入力の活用です。
従来は夜勤明けにまとめて記録を書くケースが多く、結果として残業や記録漏れの原因となっていました。
特に疲労がピークに達する明け方の作業は正確性を欠きやすく、ヒューマンエラーにつながるリスクも高かったのです。
タブレット端末やスマートフォンから直接入力できるシステムや、会話をそのまま記録に変換する音声入力機能を導入することで、対応の直後に簡単かつ迅速に記録が可能になります。
実際に、ある特養では記録にかかる時間を約30%削減し、残業削減と同時に「利用者と会話する時間が増えた」との声も上がっています。
介護ソフト開発会社の調査によれば、記録電子化を導入した施設の8割以上が「スタッフ間のコミュニケーションが増えた」と回答しています。(出典:ワイズマン「介護ソフト活用調査」 wiseman.co.jp)
AI・ロボット支援
また、身体的な負担を軽減するソリューションとして注目されているのがAIやロボットの導入です。
移乗や体位変換、入浴介助といった業務は腰や肩に大きな負担がかかり、腰痛が離職理由になる職員も少なくありません。介助ロボットやリフトを導入することで、力仕事の多くを機械が担い、職員は安全にサポートできるようになります。
これにより身体的疲労が減少し、長期的な就労継続につながると期待されています。
導入当初は操作に慣れる必要がありますが、「腰の痛みが減った」「夜勤明けも体が楽になった」といったポジティブな声が多く、職員のモチベーション維持にも寄与しています。
装着型移乗支援ロボットの導入では、脊柱起立筋の負担が平均31%軽減されたとのデータもあります。(出典:アシストスーツの窓口 cf-robo.com)
シフト管理・勤怠DX
最後に挙げたいのが、シフト管理や勤怠におけるDXの活用です。
管理者は日々、スタッフの勤務希望や休暇申請を考慮しながらシフトを作成していますが、人数が多い施設ではその調整に膨大な時間がかかります。
AIを活用したシフト自動生成システムを導入した施設では、スタッフの希望とスキルをもとにバランス良く勤務を割り振れるようになり、管理業務にかかる時間を半減させることに成功しています。
また、勤怠管理と連動することで、労務上の不公平感を減らし、職員満足度の向上にもつながっています。
実際にAIシフト自動作成ツールを導入した事例では、シフト作成時間が従来の半分に短縮されたという報告もあります。(出典:厚生労働省『介護現場におけるICT導入実証事業報告書』)
第4章:導入における課題と今後の展望

もちろん、DX導入には明るい側面だけでなく、いくつかの課題も存在します。現場でよく指摘されるのは以下の3点です。
1.コスト面
最大のハードルは初期投資の大きさです。見守りセンサーや介助ロボット、電子記録システムなどの導入には、数百万円単位の資金が必要になる場合もあります。特に中小規模の施設では「費用対効果が見えにくい」と感じ、導入をためらう声も少なくありません。また、維持費やシステム更新費用も継続的に発生するため、導入判断は容易ではありません。
2.教育・研修
次に挙げられるのが、職員への教育・研修です。介護の現場にはICTに不慣れな世代の職員も多く、「機械操作に自信がない」「システムが難しそう」という心理的ハードルがあります。いくら優れた機器でも、現場で使いこなせなければ意味がありません。導入時に十分な研修機会を設けること、操作がシンプルで分かりやすい製品を選定することが成功の鍵となります。
3.セキュリティ
そして忘れてはならないのが、個人情報保護とセキュリティの問題です。センサーや電子記録システムは膨大な利用者データを扱うため、不正アクセスや情報漏えいのリスクが常に伴います。セキュリティ対策を怠れば、施設の信頼を大きく損なうだけでなく、法的責任を問われることにもなりかねません。そのため、堅牢なセキュリティ体制を備えたシステムを選び、定期的に点検・更新を行うことが不可欠です。
課題をどう乗り越えるか
とはいえ、これらの課題は決して越えられない壁ではありません。
重要なのは、「現場の声を反映しながら段階的に導入すること」です。
いきなり全てを置き換えるのではなく、まずは特定フロアや小規模な範囲で試験導入を行い、実際の効果を職員と共有します。
そのうえで、使いやすさや課題点を洗い出し、小さな成功体験を積み重ねていくことが定着の近道です。
導入プロセスを通じて「記録時間が減った」「夜勤が少し楽になった」といった実感を得られれば、職員の抵抗感も和らぎ、自然とDX活用が広がります。
最初から完璧を目指すのではなく、現場と共に育てる姿勢が欠かせません。
さらに、導入の価値を理解するためには、立場ごとの視点 を整理することも重要です。
- 経営層にとっては、導入コストと効果のバランスが最大の関心事です。投資に見合う成果が出るかどうかが判断の軸になります。
- リーダー層にとっては、現場をまとめるうえで情報共有やシフトの公平性が改善される点が大きな価値となります。
- スタッフ層にとっては、日々の業務負担が軽減され、安心して働ける環境が整うことが最も大きなメリットです。
このように立場ごとの期待や不安を整理して導入を進めることで、関係者全員が納得感を持ちながらDXを受け入れやすくなります。
第5章:まとめ

夜勤や長時間労働の負担は、介護業界における最大の課題のひとつです。
慢性的な人材不足のなかで、限られた職員が心身の限界に近い状態で現場を支えているという現実は、業界全体の持続可能性を揺るがす深刻な問題といえます。
こうした状況に対し、DXの活用は単なる流行語ではなく、現場の未来を切り開くための大きな可能性 を秘めています。
重要なのは、現場のリアルな声を出発点にすることです。
机上の理論だけでシステムを導入しても、職員が「使いにくい」「現場に合わない」と感じれば定着せず、むしろ新たな負担を生んでしまいます。
だからこそ、現場で実際に働く職員の声に耳を傾け、記録や巡回、突発対応といった日常業務の中で何が一番の負担なのかを明らかにし、その優先度に合わせて導入を進めることが不可欠です。
また、DXは「人の代わりをする」ものではありません。
テクノロジーに任せる部分と、人だからこそできるケアを切り分けることで、介護の質を落とさずに職員の働きやすさを実現できます。
センサーやAIが安全確認を補助する一方で、利用者との会話や安心感を与える寄り添いは人にしかできない役割です。つまりDXは、人の力を奪うのではなく、人にしかできない仕事をより豊かにするための後押し なのです
未来の介護現場は、「人とテクノロジーが協働する現場」として進化していくでしょう。
夜勤の巡回に追われるのではなく、センサーと連動して必要な場面に素早く駆けつける。
記録に追われるのではなく、音声入力でその場で残し、利用者と向き合う時間を確保する。
体力的に厳しい介助はロボットに補助してもらい、職員は利用者の声を聞く。
そうした未来像は決して遠い夢物語ではなく、すでに試験導入から実績を積み重ねている施設も少なくありません。 DXの実践は、一度に全てを変えるものではなく、小さな成功体験を積み重ねていくプロセスです。
その第一歩こそが、夜勤や長時間労働の負担を軽減する取り組みなのです。
現場の声を大切にしながら、人とテクノロジーが共に歩む未来を築くことが、これからの介護業界に求められています。
この記事を書いた人

atushi1172
柔道整復師として医療現場に携わった経験をもとに、介護・医療分野に関する執筆を行っています。現場での知見を活かし、介護DXや働きやすさの向上など、実態に即した情報発信を心がけています。